|
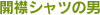
先日「着物イメトレ部屋」の犬子さんとお会いしてから、昭和30年代の日本が気になってしょうがないったらしょうがない。ついでに、彼女との会話で「大正野郎」という単語がでてきたものだから、山田芳裕熱が再燃してしょうがないったらしょうがない。山田芳裕さんとくれば、まず「度胸星」をオススメしたいがここでは「大正野郎」を。この漫画には、着物を日常的に着ている人が登場している。
あたくし、この山田芳裕さんのデビュー作を、間違いなく掲載誌で読んでおります(自慢?)。この漫画は、1988年に単行本として出版されているので、実際に雑誌に掲載されていたのは85年から88年前後でしょう(今、手許にないのでわかりません)。
芥川龍之介に憧れる主人公が、その思い込みから巻き起こす珍騒動の数々。この主人公が下宿している家のお母さんがいつも着物を着ている。お父さんだって、夏には開襟シャツにシャッポで通勤している。舞台は浅草。昭和30年代で止まってしまったかのような世界がそこに描かれている。
山田さんはその後「考える侍」という漫画を連載する。こちらは舞台は江戸時代末期。ココロの底からロマンチストの主人公が、自慢の剣技を相棒にいろいろと哲学するお話。作者御自身が「江戸時代の着物を着たかっこいい男を描きたい!」という熱い思いのもとに、この漫画は繰り広げられたに違いない!
ところで、今、上のリンク2箇所を見ていて、この単行本の表紙が、私が持ってる浴衣の柄にそっくりなことに気がついた。単行本自体は発売当時に買ってるのに、この柄には目が届いていなかった。木を見て森を見ずとはこのことだね。
それはさておき、「大正野郎」のお父さん。
現代の日本のサラリーマンは無理しすぎだー。体温近くまで気温が上昇する真夏にジャケットを羽織るのは、絶対無理してる! もっと気楽にゆるーく生きていただいても全然構いませんよ。生地だっていたむし、あなた方がジャケットを着ているために会社全体は大冷房庫になってしまっているじゃないですか。エネルギーの無駄遣いですよぅ。大正野郎のお父さんみたいな格好で通勤したら、原子力発電しなくても済むようになるってー。
しかし、あの真夏のサラリーマンのスーツ姿というのは、ある意味、武士道精神の表れなのかもしれませんね。だけど、会社は面倒見てくれない、国も面倒見てくれない、主君不在のこの時代、武士道なんてもういらないんだってば。無駄なエネルギーを遣わずに生きていきましょう。そうすれば、ヒートアイランド現象がちょっとは抑えられるかもしれません。
ちなみにgoogleで「サラリーマン
昭和 開襟」で検索すると、いろいろ面白いページがでてくる。サラリーマンはいつから、真夏に上着を着るようになったのか、そこらへんしっかりととっちめたい。
開襟シャツを着た男性をいろいろとイメージしたが、最後に、高野文子の「美しき町」に行き着いた。「棒がいっぽん」に収録されています。「美しき町」は昭和30年代の若い夫婦の物語。どうもその爽やかなイメージが強烈に頭にしみついているようだ。自分がうまれる十数年前の話なのに、とても遠い時代のように思える。
プロジェクトXなんかを見ていると、開襟シャツの男前たちがわらわら出てくるわよね。南北線に開襟シャツの男子を! 山手線にも! ぜひ! 中央線にも、東海道線にも是非是非是非!
2003.06.16
|